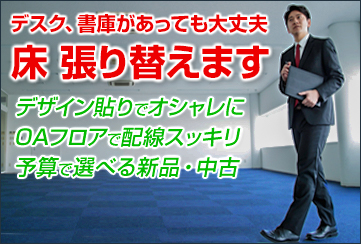空調コストを抑えながら快適な職場環境をつくるには、冷房と除湿(ドライ)の特性を理解し、上手に使い分けることがポイントです。
夏本番に向けてエアコンの使用頻度が高まるなか、空調の効き具合や電気代の違いは、日々の業務環境や経費に大きく影響します。
冷房とドライのどちらを選ぶべきか迷っている方に向けて、本記事ではそれぞれの仕組みや電気代の比較、オフィス環境への適性をわかりやすく解説。
セントラルヒーティングやビル管理の大型空調とは異なる、個別のエアコン(つまり、室外機が近くに設置されているようなタイプのエアコン)をご利用の皆さまを対象に、快適な室内環境を保つための冷房と除湿の賢い使い分けについてです。
社員が快適に過ごせて、なおかつ経費削減にもつながる空調の使い方を探っていきます。
冷房と除湿(ドライ)の違いとは?

冷房と除湿(ドライ)では、仕組みや効果、電気代のかかり方には大きな違いがあります。
特にオフィスでの空調管理を任されている立場では、快適さだけでなくコスト面も見逃せません。
ここでは、冷房と除湿(ドライ)の基本的な違いについて、わかりやすく解説します。
- 冷房とは?
- 除湿(ドライ)とは?
冷房とは?
冷房とは、室内の温度を下げることを目的とした運転モードです。
エアコン内部の熱交換器を使って部屋の空気から熱を取り除き、冷たい空気を送り出し、設定温度まで室温を下げていきます。
暑さで仕事に集中しにくい夏場には欠かせない機能ですが、消費電力が比較的高くなる傾向があるため、使い方には工夫が必要です。
除湿(ドライ)とは?
除湿(ドライ)とは、室内の湿度を下げることを目的とした運転モードです。
空気中の水分を取り除き、温度を大きく下げずにさらっとした快適な空間をつくります。
冷房よりも冷えを感じにくいため、「寒くなりすぎるのが苦手」という方にもおすすめです。
さらに、ドライ運転には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」という2つの方式があります。これは、エアコンのドライ(除湿)モードにおける内部の運転方式を指しています。
弱冷房除湿
エアコン内部で空気を冷やして湿気を取り除いたあと、そのままの温度で室内に戻す方式
再熱除湿
空気をいったん冷やして湿気を取り除いたあと、再び暖めてから室内に戻す方式
ただし、これらをユーザーがリモコンで直接選べることは少なく、実際にはエアコンの機種ごとにどちらかの方式があらかじめ採用されているのが一般的です。
電気代や快適性に差が出るため、できれば取扱説明書やメーカーの公式サイトで、自分の使っているエアコンがどちらの方式なのか確認しておくのがおすすめです。
冷房と除湿(ドライ)の電気代はどちらが安い?

冷房と除湿(ドライ)の電気代は、「どちらが安い」とは一概に言えません。
使っているエアコンの機種や、設定温度、室温、湿度など、さまざまな条件によっても電気代は変わってきます。
さらに、ドライ運転には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」という2つの方式があり、それぞれ消費電力に大きな差があります。
冷房、除湿(ドライ)の電気代についてそれぞれ解説します。
冷房の電気代
冷房は一定の温度を保つためにコンプレッサーを断続的に稼働させるため、消費電力が大きくなりやすいのが特徴です。
ただし、室温が安定すれば運転が緩やかになるため、長時間つけっぱなしにしても急激に電気代が跳ね上がるわけではありません。
以下の表は、冷房にかかる電気代の目安です。
|
期間 |
電気代 |
|
1時間あたり |
10.6円 |
|
1日(8時間)あたり |
84.8円 |
|
1か月(30日)あたり |
2,544円 |
除湿(ドライ)の電気代
ドライ運転の電気代は一律ではなく、採用されている除湿方式によって大きく異なります。
■弱冷房除湿
空気を軽く冷やして湿気を取り除く方式で、消費電力が少なめ。冷房よりも電気代が安くなる傾向があります。
以下の表は、弱冷房除湿にかかる電気代の目安です。
|
期間 |
電気代 |
|
1時間あたり |
5.3円 |
|
1日(8時間)あたり |
42.4円 |
|
1か月(30日)あたり |
1,272円 |
■再熱除湿
湿気を取り除いたあとに空気を再加熱してから室内に戻す方式。温度を下げすぎずに除湿できますが、再加熱に多くの電力を使うため、冷房よりも電気代が高くなる傾向があります。
以下の表は、再熱除湿にかかる電気代の目安です。
|
期間 |
電気代 |
|
1時間あたり |
14.9円 |
|
1日(8時間)あたり |
119.2円 |
|
1か月(30日)あたり |
3,576円 |
つまり、電気代の安さは「弱冷房除湿 < 冷房 < 再熱除湿」の順になります。
そのため、ドライ=省エネとは限らない点に注意が必要です。自分の使っているエアコンがどちらの除湿方式かを確認したうえで、状況に応じて冷房と使い分けるのが賢い選び方です。
エアコンの電気代を安くする方法

エアコンは、設定の見直しや使い方の工夫次第で、電気代を節約できます。
快適さを保ちながら電気代を抑えるためのポイントをわかりやすく解説しますので、ぜひ今日から取り入れてみてください。どれもすぐに実践できる内容ばかりです。
- 設定温度を見直す
- 自動運転を利用する
- こまめなオンオフを控える
- フィルターを定期的に掃除する
- 室外機の周囲を片付ける
設定温度を見直す
エアコンの電気代を抑えるうえで、もっとも手軽で効果的なのが「設定温度の見直し」です。
冷房時の設定温度を1℃上げるだけで、約10%前後の電力消費を抑えられるともいわれています。
暑い日は、温度を低めに設定しがちですが、室温を26〜28℃程度に保つことが、快適さと省エネのバランスを取るポイントです。
また、冷えすぎによる体調不良や寒暖差によるだるさも防げるため、オフィス環境の快適性向上にもつながります。
扇風機やサーキュレーターを併用して空気を循環させると、設定温度が高めでも涼しさを感じやすくなり、さらに効果的です。
自動運転を利用する
エアコンの電気代を抑えたいなら、自動運転モードを活用するのが効果的です。
自動運転は、設定した温度に合わせて風量や運転の強さを自動で調整してくれるため、無駄な電力消費を抑えつつ快適な室温をキープできます。
手動で風量を「強」や「弱」に固定してしまうと、必要以上に稼働したり冷えすぎたりして、かえって電気代が高くなるケースもあります。
外気温の変化が大きい日こそ、エアコンにまかせるほうが効率的といえるでしょう。細かく調整する手間も省けるので、日常的に取り入れやすい節電方法のひとつです。
こまめなオンオフを控える
エアコンの電気代を節約したいなら、こまめなオンオフは控えたほうが賢明です。
頻繁に電源を入れ直すと、立ち上がり時に大きな電力がかかるため、結果的に電気代がかさみます。
たとえば「ちょっと席を外すから」といってすぐに電源を切るよりも、短時間の外出や離席であればつけっぱなしのほうが効率的な場合が多いです。
現代のエアコンは、省エネ性能が向上しており、室温が安定すれば自動的に運転を緩めて消費電力を抑える設計になっています。
無駄をなくすには、長時間使わないときにだけ電源を切る、という使い分けがポイントです。
フィルターを定期的に掃除する
エアコンの電気代を抑えるには、フィルターの定期的な掃除が欠かせません。
フィルターにホコリや汚れがたまると、空気の流れが悪くなり、冷却効率が低下します。
その結果、エアコンは余計なエネルギーを使って運転するため、電気代が余分にかかってしまいます。
メーカーによって差はありますが、2週間〜1カ月に一度を目安に掃除するのが理想的です。
フィルターが清潔な状態なら、空気の循環もスムーズになり、冷暖房の効きも良くなります。
室外機の周囲を片付ける
エアコンの効率を高めて電気代を節約するには、室外機の周囲を片付けて風通しをよくすることが大切です。
室外機は、空気中の熱を外へ放出する役割を担っています。
そのため、まわりに物が置かれていたり、雑草やごみなどで風通しが悪くなっていたりすると、放熱効率が下がり、エアコンの負荷が増えて余分な電力を消費する原因になります。
特に夏場は、直射日光や熱気がこもりやすいため、室外機の前をふさがないようにするだけでなく、日よけを設置するのも効果的です。ただし、風の通り道をふさがないように注意しましょう。
冷房と除湿(ドライ)は目的に合わせて賢く使い分けよう

冷房と除湿(ドライ)は、それぞれ目的や仕組みが異なります。しっかり涼しくしたいときは冷房、湿気が気になるときは除湿を使い分けるのが効果的です。
さらに、除湿には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」があり、電気代や快適性に差が出るため、エアコンの特性を把握しておくことが大切です。
気温や湿度、そのときの必要性に応じて使い分け、快適な空間と省エネの両立が可能になります。
オフィスレスキュー119Happyでは、オフィス移転・レイアウト変更はもちろんのこと、それに伴うエアコンの新規設置や移設、撤去工事まで一貫して対応可能です。窓口を一本化することで、お客様の負担を大幅に軽減できます。オフィスのことなら、お気軽にご相談ください。